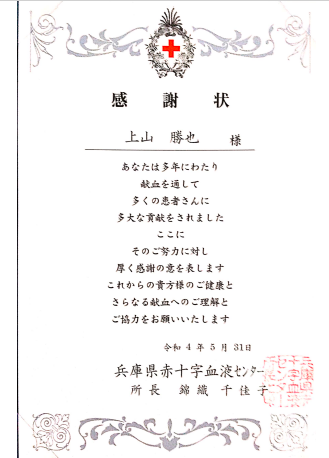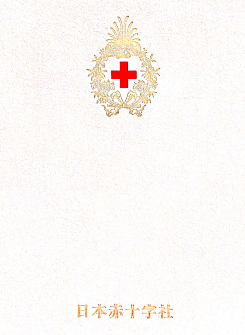JUASにて、「ネットワーク診断・セキュリティに対応するネットワークログ活用講座【オンラインライブ】 (4122205)」を担当させていただきます。
ご参加・ご紹介を頂ければ幸いです。
本セミナーでは、各種ログのポイント、パケット状況のパターン解説、効率的な解析手法など、ネットワーク診断、トラブルチェック、セキュリティチェックに特化した解説を行います。
◆主な研修内容:
第1部 ネットワーク管理の基本
ネットワーク管理全体像について解説します。
1.ネットワーク管理の重要性
2.ネットワーク管理エネルギー増大の法則について
3.ネットワーク管理の全体像
4.障害管理・性能管理と構成管理・機密管理・課金管理
5.代表的な管理ツールの紹介(役割の違いも説明)
6.SNMP、パケットキャプチャ、ログについて
第2部 ログによる解析と監視
1.ログ管理とその目的
2.ログの種類
3.ログファイル管理(集約化についても)
4.ログ解析(デジタルフォレンジックについても)
5.SIEMについて
第3部 監視技術と防御技術
1.監視技術について
2.スキャン方式について(ウイルススキャン、アクセススキャン、メールスキャンについても)
3.防御技術について
4.フィルタリングについて
5.コンテンツフィルタリングについて
第4部 ネットワーク防御構成と、ログポイント(集めるツール、集める場所)
1.セグメント分割・DMZについて
2.インターネット接続の防御ポイント
3.各種サーバ(Web、メール、DNS)分割化の必要性
4.リバースプロキシのログ活用ポイント
第5部 侵入検知・防止システム(監視体制とそのポイント)
1.IDSについて(種類と配置)
2.IPSについて(種類と配置)
3.フォールスポジティブとフォールスネガティブ
4.IDS/IPSログ活用留意点
第6部 効果的なログ解析(ログ整理、分析方法と危機予兆のつかみ方)
1.事前設定の重要性(準備が適切でないと、いざという時に役に立たないログ収集になっている)
2.ソーティングの活用
3.フィルタリング、検索の活用
4.定期的なログチェックの重要性
5.IPA試験から、ログ関連問題を取り上げた演習
<受講者の声>
・経験談に基づくセキュリティに対策するための概念や考え方を知ることができた。
・実業務に関連した内容で、また広範な知識をコンパクトに得られた。
・先進技術の説明ではなく、従来の技術を使い、基本防御ができているか、点検することの必要性について指摘してくれてたのでよかった。